合同会社の設立が最近は増えているみたいですね。
増えているとはいっても、まだまだ圧倒的に株式会社を設立する人たちが多いので、世の中的な認知度では合同会社はまだまだ弱いかもしれません。
たしかに私も会社と聞いたら思い浮かべるのは株式会社です。
一昔前は有限会社なるものがあったみたいですけど、今は法律が変わって新しく立ち上げることはできなくなったらしいですね。
その代わりに登場したのが合同会社って認識ですけど、会社の果たす機能としては有限会社と全然違うので、有限会社の代わりに合同会社を設立できるようになったというのは、ちょっと語弊があるかもしれません。
◆なぜ合同会社という呼び方になったの?
個人的な感想ですけど、合同会社が認知されにくいのはそのネーミングの悪さにあるんじゃないかと思っています。
合同会社、とか代表社員とか、株式会社!代表取締役!と比べると少しインパクトに欠けるというかダサさを感じるのは私だけでしょうか。
実際に合同会社というネーミングの由来を調べてみたのですが、ウィキペディアによると会社法を制定するときの法制審議会なるものがあるらしく、その議事録では特段積極的な意味はないと言うので驚きです。
結構ネーミングの由来って大事だと思うんですけどね。
すでに会社の種類として、合資会社や合名会社という会社の種類があるんですけど、それぞれ「合」という文字がくっついているから新しい会社の形態にも同じく「合」という文字をくっつけることが前提で合同会社となったみたいです。
まるで自分の子ども名前を決めるときに父親の名前から一字とるような、兄弟を一郎、二郎、三郎とネーミングすると同じような感覚なんでしょうか。
◆合同会社の名前の由来は会社の特徴が由来かと思った…
私はてっきり合同会社の名前の由来は、てっきり合同会社の持つ特徴によるのかと思っていました。
株式会社と合同会社の特徴を比べたときに、株式会社は出資する人と経営する人は別々にできます。いわゆる所有と経営の分離ってやつですね。
株主だけになる人もいれば、雇われ社長みたいな感じで株は持っていないけど、会社の経営に従事する取締役や代表取締役を置くことができます。
合同会社の場合は、会社の経営に従事するときは、必ず出資しないといけません。
つまり経営する立場の人と、出資する人は一緒・・・合同・・・ってことで合同会社というネーミングだと思ったわけです。
全然違いましたね。結構適当な名付け方でびっくりしました。
会社設立の支援をする中で、一番の違いはやっぱ設立費用の違いです。超低価格で会社設立を済ませたい場合は、合同会社一択かなと思います。
自分で設立するときは会社設立freeeが使いやすい。
ちなみに、合同会社の場合は、取締役とか代表取締役とか名乗れず、なんで社員とか代表社員とか紛らわしい役職なのか不思議でした。
こちらも調べてみると、もともと社員という言葉は「会社法」という法律の中では出資する人を指す言葉らしいです。
普段、従業員という意味で社員と使いがちですが、合同会社を設立するときの文脈では出資している人という意味で使わないと混乱してしまいます。
合同会社のルール上は、出資した人は必ず経営する権利、つまり業務執行権を持つことになるので、株式会社でいうところの取締役と株主を合わせたような人を、合同会社では業務執行社員と呼んだりするんですね。
社員の中でも、業務執行権を持たない設定にすることもできるので、業務執行権を持たない社員という立場もあります。これなら株式会社でいう出資しているだけの株主のようなイメージですよね。
残念ながら合同会社の場合は、出資をせずに経営に関わる立場にだけなることはできません。出資はしないで、経営に関わることをしたいなら、合同会社ではなく株式会社を選ばないといけないわけですね。
今回は合同会社の名前の由来を調べてから、随分と話題が飛んでしまいましたが、私が参考にさせてもらった合同会社の特徴はこちらのサイトになります。

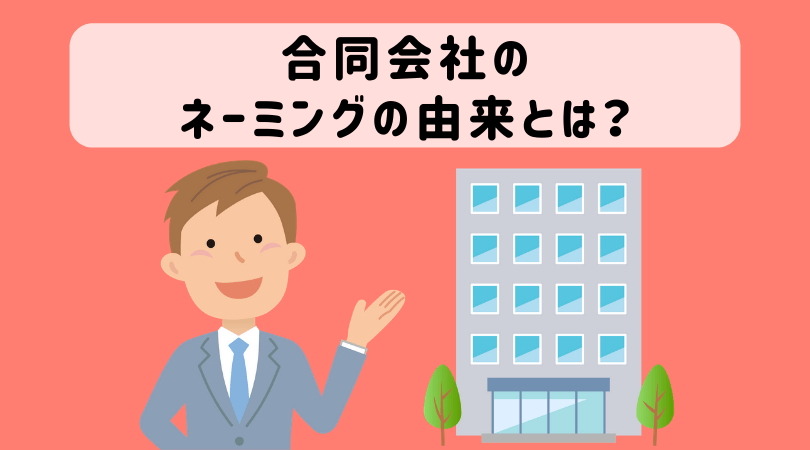






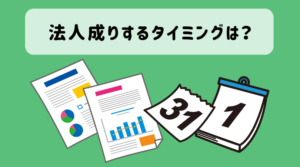

コメント